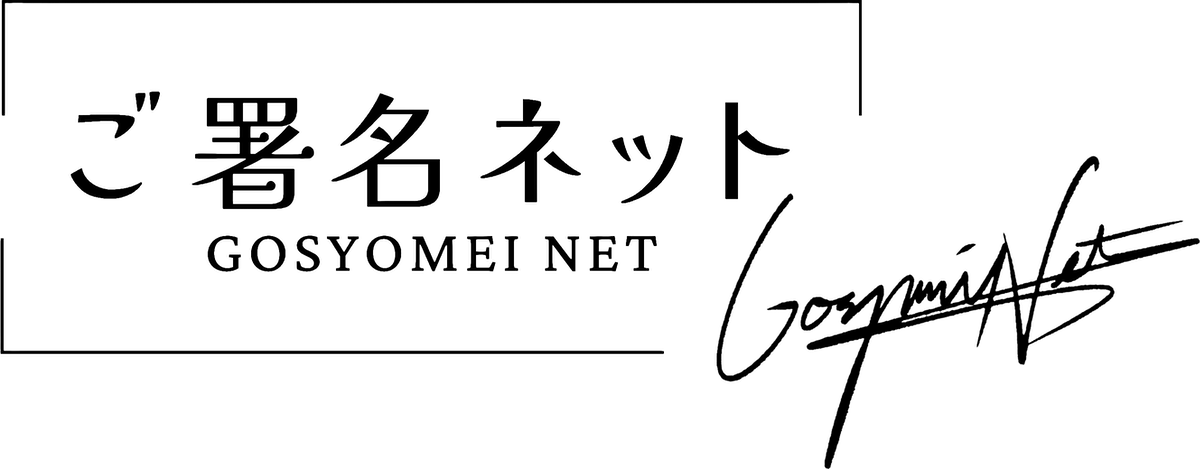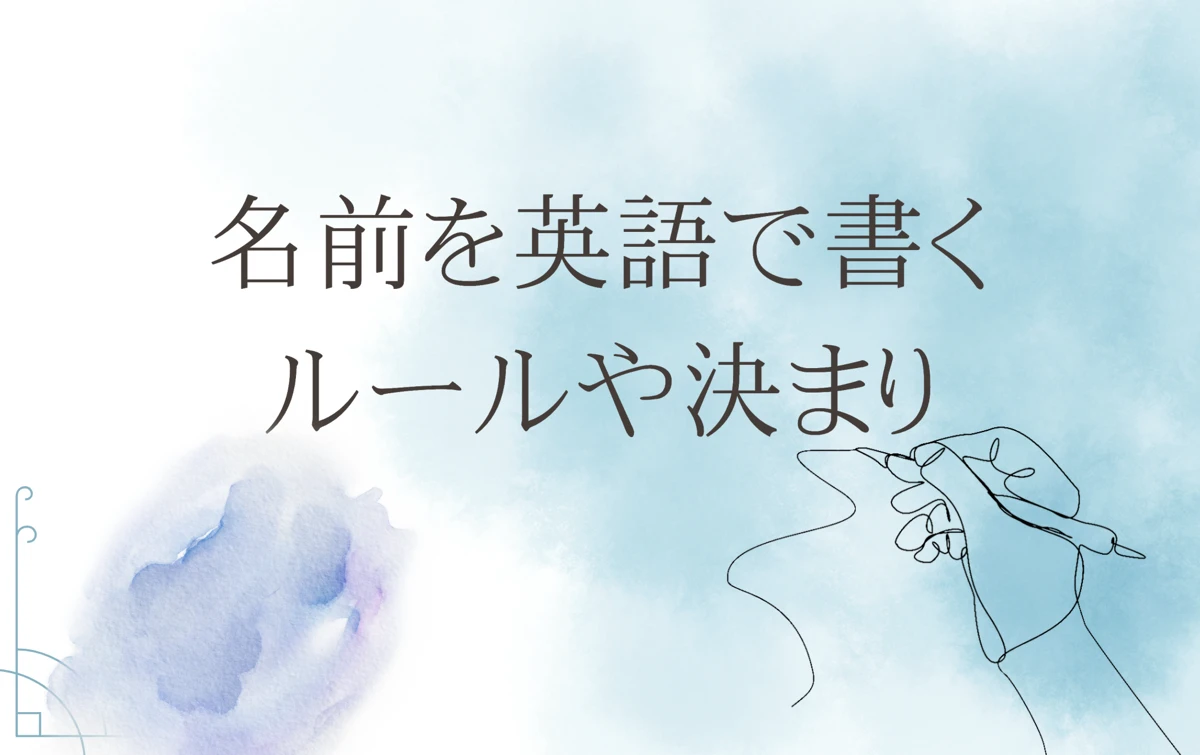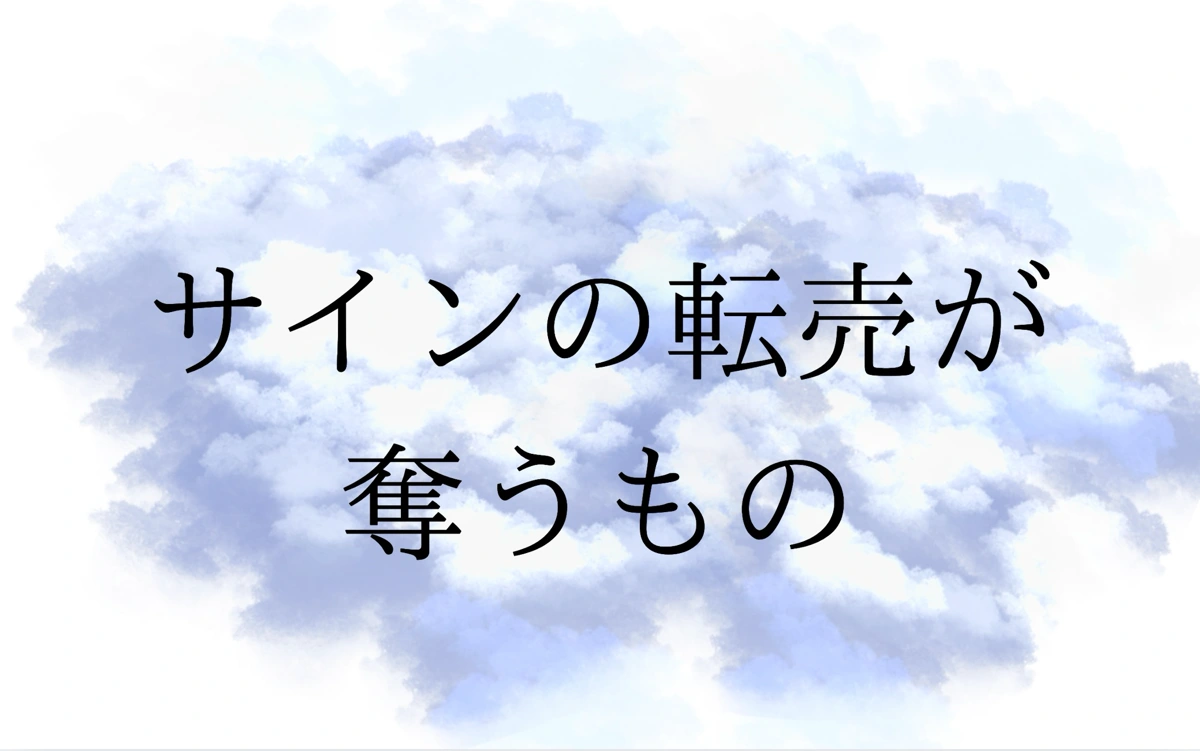日本人の名前を英語(アルファベット)で表記する機会は、パスポートやビザ申請、国際的な書類、名刺、論文執筆など意外と多く存在します。
しかし、英語表記における姓名の順番やスペルにはどんなルールがあるのか、迷う方も多いでしょう。
実は2020年、日本政府が公用文でのローマ字表記に関して方針を示し、名前の書き方に変化がありました。
本記事では、日本人の名前を英語表記する際の基本ルールと、政府の公式見解を踏まえた注意点を解説します。
加えて、以下の疑問について調査結果をもとに回答します。
- 英語表記で名前と名字の順番を入れ替えても問題ないか?
- 名前を省略するときのルールは?(イニシャルの使い方など)
- サインに記号やマークを添えても良いか?
- デザイン性が強いサインは公式文書で使用できるか?
これらのポイントを押さえておけば、国際社会で日本人の氏名を正しく表記・署名する際に自信を持って対応できるようになるでしょう。
まず結論から
先にご署名ネットのなりの結論を出しておきます。
- ローマ字つづりはヘボン式を使用するのが基本。パスポートをはじめ公式に認められた方式で、表記ゆれを避けるためにもヘボン式に従おう。
- 氏名の順序は「姓→名」が原則(政府方針)だが、状況によって名→姓でも問題ない。公式な場では伝統にならい姓から書き、カジュアルな場では相手に合わせて柔軟に。
- 名前を省略するときはイニシャルを用いる。名前(名)の頭文字と苗字を組み合わせるのが一般的(例:Taro Yamada→T. Yamada)。ただし公式書類ではフルネーム表記が原則で、省略はしない。
- サインに記号・マークは基本NG。ハートや星などを添えた署名は本人確認を困難にし、公式には推奨されない。どうしても入れたい場合は事前相談とそれなりの理由・実績が必要。
- 凝ったデザインのサインは自己責任で。法律上はどんなデザインでも署名として有効だが、再現性や可読性が低いと公式場面でトラブルになる可能性がある。公式文書に登録するサインは、できるだけ安定して書ける形にするのが安心。
以下で詳しく解説します。
日本人の名前の英語表記:基本ルールと政府の公式見解
まず、英語表記における日本人氏名のローマ字つづりについて確認しましょう。
ローマ字のつづりについて
日本人の名前をアルファベットで書く場合、ヘボン式ローマ字を使用するのが一般的です。
ヘボン式とは、日本語の発音を英語の綴りに近い形で表記する方式で、たとえば「し」はshi、「ち」はchiのように表します。
実際、旅券法ではパスポートの氏名表記にヘボン式ローマ字を用いることが定められており、公式な英字表記はこの方式に従っています。
そのため、パスポートやビザ申請書など公式書類では、戸籍上の氏名をヘボン式で正確に綴る必要があります。
姓名の順序
次に、姓名(名字と名前)の順序についてです。
日本語では古来より「姓(苗字)→名(名前)」の順で、他方、英語をはじめとする欧米では「名→姓」の順(First name – Last name)が一般的です。
従来、日本人が英語で自分の名前を書くときも、この欧米の慣習に合わせて名→姓(例:「太郎 山田」を「Taro Yamada」)と表記するのが一般的でした。
学校教育でも長年そのように教えられてきたため、多くの人にとって馴染みのある書き方だったと言えます。
しかし、2019年に日本政府が公文書での氏名ローマ字表記方針を見直し、伝統に則った「姓→名」の順で表記することを公式に決定しました。
令和元年(2019年)10月の政府申し合わせにより、2020年1月1日以降、政府の作成する公用文では日本人氏名を原則として「姓―名」の順でローマ字表記する運用が始まっています。
例えば「山田 太郎」ならYamada Taroと表記するということです。
この方針転換は「グローバル社会において各国の文化的慣習を尊重する」という観点から行われたもので、日本人の名前も自国の伝統的な順序で表記していくことが重視された結果です。
▶「公用文等における日本人の姓名のローマ字表記に関する関係府省庁連絡会議:出展:文化庁国語課」
もっとも、政府が方針を示したとはいえ、直ちに全ての場面で姓名順を逆転させなければならないというものではありません。
公文書作成など政府内部のルールとして定められたものであり、一般の民間においては「差し支えのない限り」姓→名の順を使うよう配慮が求められるにとどまります。
そのため、名刺や日常の英文メールなどで名→姓の順を用いても罰則があるわけではなく、状況に応じて柔軟に使い分けて構いません。
実際、政府内でも既存の表記を無理に全て書き換える必要はないとされており、各人や各機関の判断に委ねられています。
要点としては、正式な場では「姓→名」の英語表記が推奨される一方、カジュアルな場面や相手に応じて「名→姓」の従来表記も依然使用されているということです。
英語圏の相手に自己紹介する際などは、あえて従来通り「名→姓」で名前を伝える方がスムーズな場合もあります。
その際、自分の姓と名を認識してもらう工夫として、姓をすべて大文字で書く方法があります。
例えば「YAMADA Taro」のように記載すれば、どちらが姓(苗字)か一目で判別できます。
この手法は政府の公用文ガイドラインでも推奨されており、必要に応じて姓を全て大文字表記して姓名の構造を明示するよう定められています。
名前の前後を入れ替えても問題ないか?(名字→名前、名前→名字の順番)
結論から言えば、日本人の氏名を英語表記する際に名字と名前の順序を入れ替えても法的な問題はありません。
つまり、「名→姓」(例:Taro Yamada)と「姓→名」(例:Yamada Taro)のどちらで書いても大丈夫です。
上述のように政府は公式文書で「姓→名」を原則としましたが、これはあくまで原則であり、個人が海外で名前を書く全ての場合に強制されるものではありません。
実際、英語の契約書における署名でも、旧来通りの名→姓でも新方針の姓→名でも支障はないとされています。
要は文脈と目的に応じて、相手に誤解が生じない書き方を選べば良いということです。
例えば、英語圏のフォーマルな文脈では依然として「First Name, Last Name」の順序が標準的なので、履歴書やビジネス文書で名→姓順にしておいた方が相手にとって自然に映るでしょう。
一方、国際会議の名札や政府発行の資料では、日本人である旨が明確になるよう姓→名で表記する場面が増えています。
どちらの順にするか迷った場合は、その書類や場面の慣習に合わせるのが無難です。
仮に従来の名→姓で書いてしまったとしても、それだけで本人確認ができなくなるような重大な問題になるケースは稀でしょう。
現在は過渡期であり両方の表記が併存していますが、将来的には公式の場を中心に姓→名の表記が一般化していくと見込まれています。
また、公的なフォームではLast Name (Surname)とFirst Name (Given name)を分けて書く欄があるため、それに従えば自ずと順番の問題は解消します。
結局のところ、名前の前後を入れ替えること自体は問題ありませんが、公式見解としては「なるべく姓から書くのが望ましい」と覚えておくと良いでしょう。
名前の省略方法にはどんなルールがあるか?
英語で名前を表記する際、フルネームを書かずに省略形を使う場合のルールも押さえておきましょう。
一般に、英語圏では人名を省略する際はイニシャル (initial)を用います。
イニシャルとは名前や苗字の頭文字のことで、通常、それぞれを大文字1字で表しピリオドを付けます。
日本人の氏名にはミドルネームが無い場合がほとんどなので、たとえば「山田 太郎 (Yamada Taro)」であれば「T. Yamada」のように名前(名)の頭文字 + 姓のフルスペルという形で省略するのが一般的です。
苗字を省略することは稀で、氏名をイニシャルで書くときは苗字(姓)はそのまま書き、名前(名)やミドルネームを頭文字に置き換えるのが原則です。
仮にミドルネームがある場合(日本人でも海外でミドルネームを持つケースがあります)、名前とミドルネームの順にイニシャルを並べ、最後に姓を綴ります。例えば「山田マイケル太郎」なら「Y. M. Taro」あるいは文脈によっては「Y.M.T.」と表記されます。
公式書類では原則フルネームで表記することが求められる点に注意が必要です。
ビザ申請書、銀行口座開設書類などでは、戸籍どおりの氏名をローマ字でフルにつづることが要求され、省略は認められません(パスポートは省略ネームも受け入れられますが、自治体により対応が異なります。詳しくは後述します)。
これは本人確認を厳密に行うためで、「山田 太郎」であれば必ずYamada Taroとすべて記載し、「T. Yamada」のような略記は無効となります。
実際、金融機関の口座申込書などでは署名にフルネームを求められる場合がありますが、これは安全のためであり、万一略記で署名したとしてもすぐに問題になるケースは少ないようです。
それでも心配な場合は、迷ったらフルネームを書いておくのが無難でしょう。
フルネームで署名・表記しておけばまず間違いはありませんし、正式な場ではフルネームが望ましいとされています。
▶ヘボン式サイン見直し完全ガイド|サイン専門家が示す最新設計と実践
ただし、日常的なメールの署名やメモ書き程度であれば名字だけを書く、あるいは名前の頭文字+名字といった略し方でも差し支えありません。
要は、正式度に応じて使い分けることが大切です。
また、イニシャルを使う際の細かなマナーとして、ピリオドの有無やスペースの使い方があります。
基本的には「T. Yamada」のようにイニシャルの後にピリオドを付け、姓との間に半角スペースを入れます。
ただし欧米でもピリオドを省略する流儀もあり、統一されてはいません。
ビジネス文書ではピリオドありの方がフォーマルと言われますが、大きな問題ではないでしょう。
いずれにせよ、日本人の名前を英語で略記する場合は名前部分をアルファベット1文字で表し、苗字は省略しないというルールを覚えておけば十分です。
イニシャルサインを上手に作るコツについては、こちらのページで詳しく紹介しています。
▶一歩先を行くイニシャルサイン:専門家が教える独創的な作り方
記号やマークをサインに添えてもいいか?
近年、ハートマークや星の記号を名前と一緒にデザインするケースも見受けられます。
しかし、公式な署名として名前に記号・マークを添えることは基本的に推奨されていません。
特にパスポートなど重要な公的書類におけるサインでは、氏名以外の装飾的要素は控えるのが無難です。
どうしてもという場合は合理的な理由の説明や、実際にそのサインを日常的に使用している証拠(クレジットカードの署名など)を求められるケースもあります。
窓口の判断にもよりますが、特別な理由が無い限り記号入りのサインは受理されない可能性が高いでしょう。
パスポートのサイン/署名の書き方ルールを詳しくまとめた記事を公開していますので、あわせて御覧ください。
▶パスポートのサイン/署名の書き方の基本的ルールを紹介します
なぜサインに記号を入れることが敬遠されるのか?
その理由の一つは、サインの確認が難しくなるためです。
署名は本人が自筆で書いた証として、その筆跡や書体の一致によって本人確認が行われます。
ところが、余分な記号やマークが入っていると、見る側が「これは同一人物のサインか?」を判断しづらくなり、場合によっては筆跡鑑定上の混乱を招きかねません。
特に海外では、日本のパスポートのサイン欄にハートマークなどが描かれていると、入国審査官が不審に思い細かく照合する、といったトラブルになる可能性もゼロではありません。
さらに、記号やイラストは毎回同じ形状・位置で描くのが難しく、サインの再現性(いつも同じように書けるか)を損ねる恐れがあります。
サインは何度書いても同じ形になることが重要視されますが、複雑な記号を含むと微妙なズレが生じやすく、「パスポートのサインが申請時と微妙に異なる」と見なされて問題視されるリスクがあります。
以上の理由から、公式なサインに装飾的な記号を加えるのは避けた方が良いでしょう。
ただし、一律に「絶対ダメ」というわけではなく、どうしても必要な場合には事前に相談する道もあります。
例えばパスポート署名に本名と記号を入れたい場合などは、申請時に窓口で事情を説明し、過去に同じサインを使っているクレジットカードや公的証明書を提示することで認められる例も報告されています。
とはいえ、その場合でも手続きが煩雑になりますし、担当者の判断で奇抜なサインは受理不可となる場合もあります。
以上を踏まえ、特段の理由が無い限りはサインに余計な記号やマークは添えないのが賢明です。
一般的でない書き方(デザイン性が強いサイン)は公式文書で使用できるか?
サインは本来、自分の氏名を本人が自筆で記したものであれば、その形やデザイン自体に制約はほとんどありません。
極端に言えば、判読不能な崩し字や絵のような署名であっても、それが本人の常用する署名であり意思表示であれば法的には有効です。
実際、海外の著名人や芸術家などのサインを見ると、アルファベットには到底見えないような独特のデザインになっている例もしばしばあります。
日本人でも近年は個性を表現したおしゃれなサインを作る人が増えており、英字であっても判読性よりデザイン性を重視した筆記体やロゴ風の署名を用いるケースがあります。
結論から言えば、「一般的でない書き方」のサインであっても公式文書で使用すること自体は可能です。
ただし、実務上・運用上の注意点があります。
まず、公的な場では署名の再現性と本人確認が重視されます。
あまりに複雑すぎるサインは毎回同じように書くことが難しく、パスポート申請時に不受理となる可能性もあります。
たとえば凝りに凝ったデザインのサインを申請書に書いて提出しても、「このサインを今後一貫して使えますか?」と念押しされ、場合によっては書き直しを求められるケースがあるのです。
また、仮に受理されたとしても、渡航先で入国審査官がパスポートのサインを見た際に「文字ではなく記号のようだ」と感じると追加の質問を受けたり、クレジットカード利用時に店員に裏面署名を怪しまれ照合に時間がかかったりするリスクも考えられます。
そのため、公式文書に使用するサインは、たとえデザイン性を追求するにしてもある程度の読み取りやすさ・再現のしやすさを備えたものにすることが望ましいです。
どうしても凝ったサインを登録したい場合、前項で触れたように申請前に窓口で相談することを強くおすすめします。
実際、パスポートセンターでは「このようなデザインのサインを使いたいが大丈夫か?」といった事前相談に応じてくれます。
その際、自身のクレジットカードや過去の署名入り書類で同じサインを使用している例を提示できれば、説得力が増すでしょう。
それでも最終的には担当者判断となり、「あまりに奇抜なサインは受理できない」とされる可能性もあります。
要は、デザイン重視のサインを公式文書で使うことは可能だが、自己責任で慎重に行うべきということです。
特にパスポートや公証人の前での署名など、一度登録すると簡単に変更できない場では、そのサインで今後問題なく身分証明ができるかをよく考える必要があります。
パスポートは一度発行されると有効期限まで署名を変えられないため、「サインのデザインを失敗したから作り直したい」という要望には、例え手数料を支払ったとしても応じてもらえません。
その点も踏まえ、公式なサインには奇をてらいすぎないデザインを選ぶほうが安心と言えるでしょう。
ご署名ネットでは、周りから見られても恥ずかしくない、デザイン性のあるサインを作成いたします。
サインの形がうまく決まらない人は、ぜひご署名ネットにお任せください。
まとめ:日本人名の英語表記とサインのポイント
日本人の名前を英語表記する際のルールについて、主要なポイントをまとめます。
- ローマ字つづりはヘボン式を使用するのが基本。パスポートをはじめ公式に認められた方式で、表記ゆれを避けるためにもヘボン式に従おう。
- 氏名の順序は「姓→名」が原則(政府方針)だが、状況によって名→姓でも問題ない。公式な場では伝統にならい姓から書き、カジュアルな場では相手に合わせて柔軟に。
- 名前を省略するときはイニシャルを用いる。名前(名)の頭文字と苗字を組み合わせるのが一般的(例:Taro Yamada→T. Yamada)。ただし公式書類ではフルネーム表記が原則で、省略はしない。
- サインに記号・マークは基本NG。ハートや星などを添えた署名は本人確認を困難にし、公式には推奨されない。どうしても入れたい場合は事前相談とそれなりの理由・実績が必要。
- 凝ったデザインのサインは自己責任で。法律上はどんなデザインでも署名として有効だが、再現性や可読性が低いと公式場面でトラブルになる可能性がある。公式文書に登録するサインは、できるだけ安定して書ける形にするのが安心。
以上の点を踏まえれば、日本人の氏名を英語で表記・署名する際に戸惑うことも減るでしょう。
国際社会では、自分の名前を相手に正しく伝えることが信頼関係の第一歩です。
今回解説したルールやマナーを押さえて、場に応じた適切な氏名表記を心がけてください。